レポート/メールマガジン
REPORTS
プロがまとめた調査・考察レポートを無料公開中
レポート/メールマガジン
No.
163
スタートアップ企業における新株予約権付融資の会計処理及び評価(2024年10月31日号)
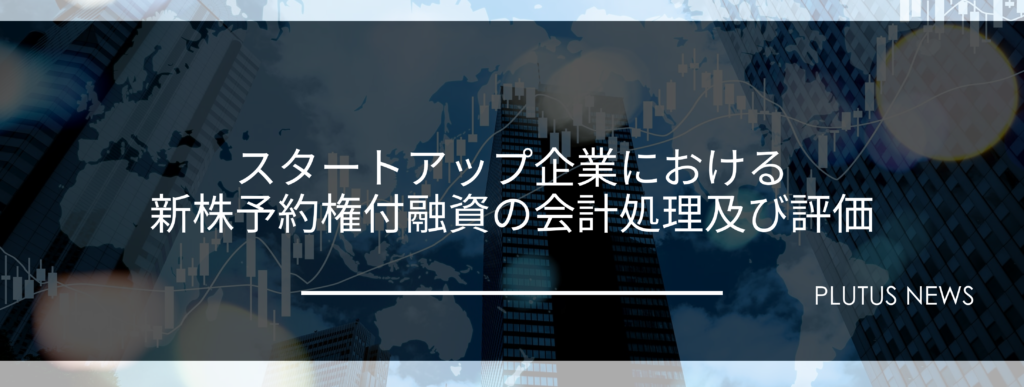
はじめに
近年、国内のスタートアップにおいて、ベンチャーデットによる資金調達が注目されております。ダウンラウンドでの資金調達を避けて次回資金調達までの期間を確保したり、上場を急ぐことなく適切なタイミングでのIPOを目指して、ベンチャーデットを活用した資金調達を行う場合が実務上、散見されています。
ベンチャーデットの1つに新株予約権付融資がありますが、本稿ではその会計処理や評価が必要となる局面、評価方法について、ご紹介させていただきます。
本稿の具体的なトピックは以下の3点となります。
➀ 新株予約権付融資とは
➁ 新株予約権付融資の会計処理について
➂ 新株予約権付融資の評価について
① 新株予約権付融資とは
新株予約権付融資とは、融資と新株予約権の付与を組み合わせた資金調達方法であり、スタートアップが融資を受ける際に、当該金融機関等に新株予約権を交付する資金調達スキームです。
新株予約権を金融機関に発行することで利息が通常の融資と比較し軽減されるという場合が想定されます。(金利の減額分を新株予約権により補っていると推察されます。)
スタートアップ側のメリットとしては以下の2点がございます。
・持株割合の希薄化を防止できる点:融資額の約30%の新株予約権を発行する場合、融資額と同額でエクイティによる資金調達する場合と比較し、約30%の経済的な希薄化で済むということになります。
また、発行体であるスタートアップが上場した後に金融機関等から当該スタートアップ等に新株予約権の売却を予定しているなど、エクイティによる資金調達と比較して、すぐには株式発行がなされないので、持株割合の希薄化が防止されると考えられます。
・資金調達が容易である点:一般的な融資を受けづらいスタートアップにおいても、融資という手法で資金調達をすることができます。また上述の通り、一般的な融資よりも金利が軽減されている点も、より資金調達がしやすい条件になっています。
一方、レンダー側のメリットとしては、新株予約権を行使して株式の売却によるキャピタルゲイン(キャピタルゲインと同額で新株予約権を発行体であるスタートアップに売却)等の収益を得ることができる点や、融資先の増加を見込むことができる点がございます。
② 新株予約権付融資の会計処理について
・新株予約権付融資は「区分法」に準じて会計処理されるのが適切と考えられています
新株予約権付融資を実行する際に締結される新株予約権割当契約書は金銭消費貸借契約書に関連して締結される等、融資と一体で契約が締結されます。
つまり、新株予約権の発行と融資の実行は同時になされ、それぞれ単独で存在しうるものであることから、新株予約権付融資は、金融商品会計基準の転換社債型新株予約権ではない新株予約権付社債である「その他の新株予約権付社債」の社債部分を融資に置き換えた金融商品に該当すると考えられ、「区分法」により会計処理されるのが適切と考えられています。1)出典:EY新日本有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 藤原 選「新株予約権付融資の会計処理・評価 ストック・オプション会計基準ではなく、
・新株予約権付融資の具体的な会計処理について
区分法の会計処理では、社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分した上で、社債の対価部分は普通社債の発行に準じて処理し、新株予約権の対価部分は新株予約権の発行者側の会計処理に準じて処理するものとされています。具体的な会計処理は下記の通りとなります。
前提条件)借入金額:100、新株予約権の評価額:3、融資期間:3年

③ 新株予約権付融資の評価について
新株予約権付融資を実行するときに新株予約権付融資の評価が求められます。新株予約権付融資に対して誤った会計処理、評価を行うと、費用計上額を遡及して修正する必要がありますので、留意する必要があります。
新株予約権の発行株数は融資の元本の数割(3割の場合が多く見受けられます。)を権利行使価格(直近の資金調達における株式の発行株価としている場合が多く見受けられます。)で割った数で算出されます。
・ストック・オプション会計基準ではなく、金融商品会計基準が適用され、新株予約権の公正な評価額が求められます
ストック・オプションを会計処理する場合、ストック・オプション会計基準が適用されますので、未公開企業では、ストック・オプションの公正な評価単価に代わり、単位当たりの本源的価値(自社株式の評価額-権利行使価格)の見積りに基づいて会計処理することが可能です。権利行使価格を発行時点の株式の評価額以上に設定されることが多いので、その場合、本源的価値はゼロとなります。
一方、新株予約権付融資は、「その他の新株予約権付社債」と同様に金融商品会計基準が適用されますので、本源的価値での会計処理ではなく、新株予約権の公正な評価額による会計処理が必要となります。
・新株予約権の公正な評価額について
新株予約権を金融機関に発行することで利息が通常の融資と比較し軽減されるという場合、融資及び新株予約権の算定が容易な一方の対価を決定し、これを払込金額から差し引いて他方の対価を算定する方法によることが多いと考えられます。2)出典:EY新日本有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 藤原 選「新株予約権付融資の会計処理・評価 ストック・オプション会計基準ではなく、金融商品会計基準が適用される?」前掲(注1)参照。金融商品会計基準によれば、①融資及び新株予約権の払込金額又はそれらの合理的な見積額の比率で配分する方法、あるいは②算定が容易な一方の対価を決定し、これを払込金額から差し引いて他方の対価を算定する方法によることになりますが、新株予約権を金融機関に発行することで利息が通常の融資と比較し軽減されるという場合、以下の理由により、②の方法によることが多いと考えられます。
複合金融商品適用指針43項なお書きによれば、社債(借入金)と新株予約権のそれぞれの払込金額が経済的に合理的な額と明らかに乖離するときには、当該払込金額の比率で配分する方法の適用は適当ではないとされ、このような場合には、新株予約権付社債(借入金)を区分する他の方法を適用することになるとされております。新株予約権を金融機関に発行することで利息が通常の融資と比較し軽減されるという場合、当該軽減分が新株予約権の価値に該当しますが、新株予約権付融資の払込金額は、新株予約権が0で、払込全額が借入金ですので、「社債(借入金)と新株予約権のそれぞれの払込金額が経済的に合理的な額と明らかに乖離する」ため、新株予約権付融資を区分する他の方法を適用することになると考えられます。
具体的には、融資の算定と新株予約権の評価を比較し、算定が容易な一方の対価のみを算定することになりますが、融資の算定は、融資(借入金)の元利合計を、「新株予約権が付されていなかった場合に設定されたであろう純粋な(プレーンな)借入金に対する金利」で割り引いて現在価値で時価を算定する方法が考えられます。3)出典:EY新日本有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 藤原 選「新株予約権付融資の会計処理・評価 ストック・オプション会計基準ではなく、金融商品会計基準が適用される?」前掲(注1)参照。借入金の時価の算定においては、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」351項の区分処理方法や、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」を参考にして、融資(借入金)の元利合計を、「新株予約権が付されていなかった場合に設定されたであろう純粋な(プレーンな)借入金に対する金利」で割り引いて現在価値で時価を算定する方法が考えられます。
つまり、新株予約権を金融機関に発行することで利息が通常の融資と比較し軽減されるという場合、当該融資の返済額と利息を、軽減される前の「通常の融資」の利率で割り引いて現在価値を算出することになりますが、当該融資の金銭消費貸借契約書には軽減後の利率は記載されているものの、軽減される前の「通常の融資」の利率は記載されておらず、金融機関に問い合わせても回答が貰えない場合には、当該融資の対価の算定は難しいので、新株予約権の評価が必要となります。(以下では、新株予約権の評価が必要という前提で、ご紹介させていただきます。)
・株価算定の必要性について
N-2期以降(上場申請を行う期(申請期)、申請期の1期前の期(N-1期)及び申請期の2期前の期(N-2期))の企業については、監査上、適切な株式報酬費用計上額の算出が求められ、原則、自社の株式価値算定及び新株予約権の評価が必要となります。一方、N-3期以前の企業については、適切な過年度遡求修正が求められ、原則、株価算定と新株予約権の評価が必要でありますが、直近の資金調達における株式の発行株価を権利行使価格としており当該発行株価の妥当性の検証までは求められない場合においては株価算定が不要となり、新株予約権の評価のみが必要となります。
なお、新株予約権の条件次第では、費用計上額が融資額の数%になる可能性がございます。
特に、発行会社が上場直前の場合、予期していない費用が生じる可能性がございますので、予実管理や上場時のバリエーションに影響を及ぼす可能性があることから、より慎重に検討をする必要があると思われます。
終わりに
国内のスタートアップ向けの新株予約権付融資のニーズの高まりを受け、今後さらに新株予約権付融資の評価が必要になるスタートアップが増加していくと思われます。新株予約権付融資の評価については、特有の論点が存在し、より慎重に検討をする必要があると思われます。
新株予約権付融資の実行を御検討の際には、是非お気軽にお問合わせください。
執筆者紹介
石田 良輔 < フィナンシャル・アドバイザリー部 エグゼクティブ・ダイレクター 公認会計士 >
京都大学大学院理学研究科修士課程修了。監査法人及び税理士法人にて、監査、アドバイザリー、税務に関する業務を経験後、現在、大手企業からベンチャー企業まで様々な局面の株価算定、虚偽記載関連の株価分析を含む株式価値を巡る裁判対応、オプション・CBワラントの設計評価まで幅広く多数従事。
石坂 和征 < フィナンシャル・アドバイザリー部 シニア・マネジャー >
早稲田大学卒業後、証券会社を経て、プルータス・コンサルティングに入社。上場会社同士のM&Aに対するフィナンシャル・アドバイザーを担当するほか、大手企業からベンチャー企業まで様々なフェーズの資本政策関連のアドバイザリー業務及びバリュエーション業務に従事し、多数の案件を手掛ける。
藤江 優貴 < フィナンシャル・アドバイザリー部 マネジャー >
大学卒業後、SMBC日興証券を経て、プルータス・コンサルティングに入社。現在はバリュエーション業務を中心に、上場企業同士のM&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー業務を担当。
中山 滉介 < フィナンシャル・アドバイザリー部 コンサルタント >
京都大学大学院を卒業後、大手信託銀行にて年金の運用業務・オペレーション業務等に従事したのち、プルータス・コンサルティングに入社。現在は、SOの権利行使価格の検討、M&Aや組織再編を目的としたバリュエーション業務を中心に担当。
株式会社プルータス・コンサルティング 広報担当
〒100-6035 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング35階
TEL:03-3591-8123
※ 本メールは、プルータス・コンサルティング社員が名刺交換および面談させて頂いた皆様にお送りしております。配信停止のご希望は こちら から承ります。
References
| 1. | ↑ | 出典:EY新日本有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 藤原 選「新株予約権付融資の会計処理・評価 ストック・オプション会計基準ではなく、 |
| 2. | ↑ | 出典:EY新日本有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 藤原 選「新株予約権付融資の会計処理・評価 ストック・オプション会計基準ではなく、金融商品会計基準が適用される?」前掲(注1)参照。金融商品会計基準によれば、①融資及び新株予約権の払込金額又はそれらの合理的な見積額の比率で配分する方法、あるいは②算定が容易な一方の対価を決定し、これを払込金額から差し引いて他方の対価を算定する方法によることになりますが、新株予約権を金融機関に発行することで利息が通常の融資と比較し軽減されるという場合、以下の理由により、②の方法によることが多いと考えられます。 複合金融商品適用指針43項なお書きによれば、社債(借入金)と新株予約権のそれぞれの払込金額が経済的に合理的な額と明らかに乖離するときには、当該払込金額の比率で配分する方法の適用は適当ではないとされ、このような場合には、新株予約権付社債(借入金)を区分する他の方法を適用することになるとされております。新株予約権を金融機関に発行することで利息が通常の融資と比較し軽減されるという場合、当該軽減分が新株予約権の価値に該当しますが、新株予約権付融資の払込金額は、新株予約権が0で、払込全額が借入金ですので、「社債(借入金)と新株予約権のそれぞれの払込金額が経済的に合理的な額と明らかに乖離する」ため、新株予約権付融資を区分する他の方法を適用することになると考えられます。 |
| 3. | ↑ | 出典:EY新日本有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 藤原 選「新株予約権付融資の会計処理・評価 ストック・オプション会計基準ではなく、金融商品会計基準が適用される?」前掲(注1)参照。借入金の時価の算定においては、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」351項の区分処理方法や、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」を参考にして、融資(借入金)の元利合計を、「新株予約権が付されていなかった場合に設定されたであろう純粋な(プレーンな)借入金に対する金利」で割り引いて現在価値で時価を算定する方法が考えられます。 |
エクイティ・ファイナンスのレポートを見る
-
はじめに 上場会社などが他の企業と資本業務提携を結ぶ際には株式の相互持ち合いや第三者割当増資だけでなく、資本業務提携の成功度合いを見ながら徐々に行使が進んでいく新株予約権を活用する事例が存在して...
-
2024年 上場企業エクイティ・ファイナンス動向調査(2025年6月号)
はじめに 2024年、インフレや金利動向、地政学的リスクなどの不確実性が高まる世界経済環境下で、多くの日本企業がエクイティ・ファイナンスを積極的に活用しました。その背景には、従来の事業成長の...
-
J-KISS等コンバーティブル・エクイティの公正価値評価(2022年11月30日号)
Topic. ► J-KISS等コンバーティブル・エクイティの公正価値評価 ...
-
上場企業における優先株式の発行事例調査2021(2021年10月29日号)
Topic. ► 上場企業における優先株式の発行事例調査2021 ...
-
上場企業における優先株式の発行事例調査/セミナーのご案内(2021年2月26日号)
Topic1. ► 上場企業における優先株式の発行事例調査 ...
-
有償新株予約権型コンバーティブル・エクイティの公正価値評価(2020年10月30日号)
Topic. ► 有償新株予約権型コンバーティブル・エクイティの公正価値評価 ...
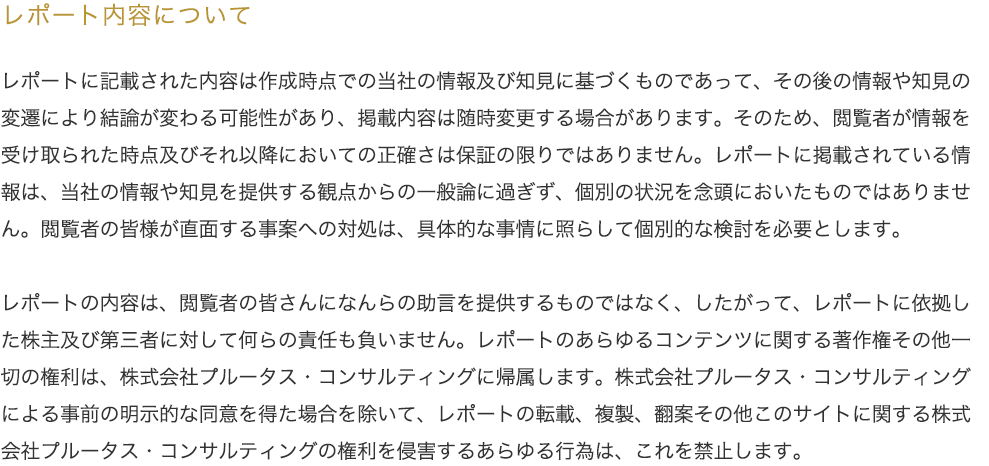
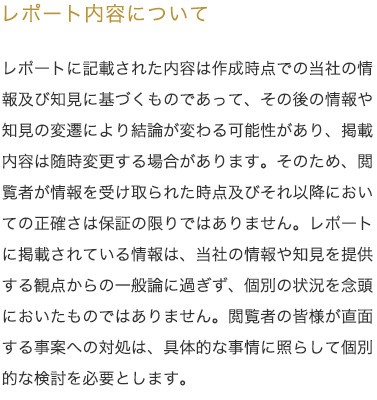
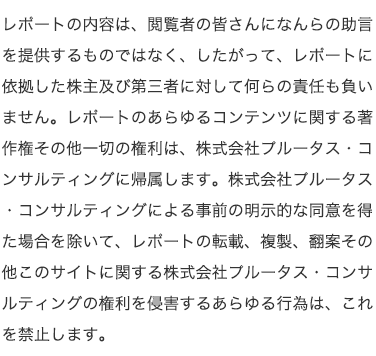
エクイティ・ファイナンスの事例を見る
-

株式会社モンスターラボホールディンクスが発行する第三者割当新株予約権の公正価値の算定
株式会社モンスターラボホールディンクス(東証グロース 5255)が山陰合同銀行に第三者割当の方式にて発行する、A種優先株式の公正価値の算定を実施しました。 なお、本資金調達は、債務超過の解消及び財政
続きを読む
-

株式会社ジーニーが発行するA種優先株式の評価
株式会社ジーニー(東証グロース 6562)がみずほ銀行に第三者割当の方式にて発行する、A種優先株式の公正価値の算定を実施しました。 なお、本資金調達は、主要株主であるソフトバンク株式会社から自己株式
続きを読む
-

KLab株式会社が発行する第三者割当新株予約権の公正価値の算定
KLab株式会社(東証プライム3656)がマッコーリー・バンク・リミテッドに第三者割当の方式にて発行する、新株予約権の公正価値の算定を実施しました。 なお、本資金調達は新規大型モバイルオンライン
続きを読む
エクイティ・ファイナンスのソリューションを見る
-
第三者割当新株予約権
第三者割当新株予約権とは 第三者割当新株予約権とは、企業が資金調達を行う際の選択肢の一つとして、年間100件程度実施されている資金調達手法です。第三者である投資家に新株予約権を割当て、投資家は権利行
-
転換社債(CB)
新株予約権付社債とは 新株予約権付社債(CB:Convertible Bond)とは、普通社債の金利に代わって、新株予約権をセットにした有価証券であり、一般的には、転換社債型新株予約権付社債と呼ばれ
-
種類株式(非上場会社、みなし清算条項)
ベンチャー企業の資本政策における種類株式の活用 会社法の施行後、ベンチャー企業の資金調達は種類株式により行われるのが一般的となりました。これは、会社を設立した創業者らと、後から出資した投資家との間で
-
ファイナンシャル・アドバイザー
ファイナンシャルアドバイザー 圧倒的な事例の蓄積 当社には、創業間もないベンチャー企業の評価から、各方面で注目された合併・買収事案におけるファイナンシャルアドバイザリーまで、業種・規模を問わず様々
-
種類株式(上場会社)
種類株式 種類株式の枠組み 会社法施行により、企業は様々な特徴を持った株式(種類株式)を発行することができるようになりました(会社法107条、108条)。企業は、自らの背景や目的に合わせた種類株式
-
第三者割当増資(株式)
第三者割当増資 上場会社の第三者割当増資においては、市場株価を参考に価格を定めるのが一般的であり、第三者機関による評価がなされるのは非上場株式を前提にした場合がほとんどです。ただし、上場会社であって

