レポート/メールマガジン
REPORTS
プロがまとめた調査・考察レポートを無料公開中
レポート/メールマガジン
No.
101
「公正なM&A の在り方に関する指針」が株式価値算定実務に与える影響
株式会社プルータス・コンサルティング
マネージング・ダイレクター 山田 昌史
1. はじめに
経済産業省は、2019 年6 月28 日、「公正なM&A の在り方に関する指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」を公表しました。本稿は多くのM&Aに企業価値評価実務家として関与してきた見地から、本指針が実務に与える影響について該当箇所を抜粋の上、検討と解説を加えることを目的としています。
1. 1 策定の経緯
本指針は、2007年9 月4 日に公表された「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」をもとに、その後10年以上かけて蓄積された実務の中で得られた公正なM&Aについての議論の整理を行い、公正な実務を実現する上で有効な対応を提示するために策定されたものです。
1. 2 企業価値評価実務における位置付け
M&Aにおける株式の公正な価格を巡っては、2016年7月1日付ジュピターテレコム事件最高裁決定において「一般に公正と認められる手続により公開買付けが行われた場合には、公開買付けに係る買付け等の価格は、多数株主等と少数株主の利害が適切に調整された結果が反映されたものと言うべきである」との考え方が示されました。これにより、その後の事案における焦点は、「一般に公正と認められる手続」が行われたといえるか否かに移りました。本指針は、株式の公正な価格を巡る裁判において「一般に公正と認められる手続」の議論がなされる際にも斟酌されることが想定されます。
2. 指針の対象となる取引
本指針では、MBOと親会社による子会社の買収がその一義的な対象とされています。
一方で、典型的なMBOや親会社による子会社の買収でなくても、これらと同様に利益相反等の問題がある場合には、本指針を参照することが推奨されています。
具体的には、子会社による親会社の資産の取得など、いわゆる支配株主との重要な取引等1)東京証券取引所 企業行動規範に関する規則第12条の2に該当する場合などが考えられます。このような場合については、本指針を参照して慎重に取引を実行することが有益と考えられます。
3. 指針が企業価値評価実務に影響を与える点
本指針「第3章 実務上の具体的対応(公正性担保措置)」では、具体的に実務で求められる手続きが詳細に整理されています。その中で企業価値評価実務にとりわけ影響を与えると考えられる点を、本稿では下記の5つにまとめました。
1.特別委員会の委員構成 アドバイザーの起用
2.特別委員会の交渉過程への関与
3.株式価値算定とフェアネスオピニオンの意義・機能
4.第三者評価機関の独立性
5.株式価値算定に関する開示
3. 1 特別委員会の委員構成 アドバイザーの起用
特別委員会の組成にあたっては、従前は社外役員1~2名と外部の法律、財務の有識者、若しくは外部有識者3名程度とする実務が一般的でした。
本指針においては従前の実務とは異なり、法的な観点等から社外取締役を中心とすべきとの提言がなされています。
しかし、このような観点から委員が構成された場合、M&Aに関する法的観点や価値算定、交渉実務に関する知識、経験を持つ委員が選任されない懸念が生じます。この点について指針では下記のように整理がなされています。
なお、特別委員会は、委員として最も適任である社外取締役のみで構成し、M&Aに関する専門性は、アドバイザー等から専門的助言を得ること等によって補うという形態が最も望ましいと考えられる。
従前の事例においては、特別委員会にM&Aの専門性を持つ有識者が入ることが多かったため、委員会自体がアドバイザーを起用する事例は極めて稀2)特別委員会が独自にアドバイザーを起用した事例としては、2011年2月3日公表カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社のMBOと、2019年2月12日公表KDDI株式会社によるカブドットコム証券株式会社に対する公開買付けがあります。でした。
本指針では、委員自体にM&Aに関する専門性を求めるのではなく、委員会は社外取締役で構成し、専門的助言はアドバイザーにより行われる形態を最も望ましいと位置づけました。
起用すべきアドバイザーについては以下のように整理されています。
今後の実務においては、特別委員会自体が第三者評価機関を起用する事例も増加してくるものと考えられます。
3. 2 特別委員会の交渉過程への関与
従前の実務においては特別委員会の役割、権限が明確化されていたわけではなかったことから、特別委員会の交渉過程への関与についての運用は曖昧であったものと認識しています。
本指針では、特別委員会が買収対価等の取引条件に関する交渉過程に実質的に関与すべき旨が明記されました。
その方法としては、特別委員会が取引条件が妥当でないと判断した場合には当該M&Aに賛同しないことを取締役会においてあらかじめ決定した上で、①特別委員会が取引条件の交渉を行う権限の付与を受け、自ら直接交渉を行うこと、または②交渉自体は対象会社の担当役員やプロジェクトチーム等の社内者やアドバイザーが行うが、特別委員会は、例えば、交渉について事前に方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うこと等により、取引条件に関する交渉過程に実質的に影響を与え得る状況を確保することが考えられ、個別のM&Aにおける構造的な利益相反の問題の程度や特別委員会の委員構成等の具体的状況に応じて、適切な方法や態様で関与することが望ましい。
特別委員会が買収対価等の取引条件に関する交渉過程に関与するにあたり、委員会の判断の実効性を担保するために、取締役会の意思決定が特別委員会の判断に拘束されるようあらかじめ取締役会で決定しておく方法が提言されています。
交渉への具体的な関与方法としては、①委員自身が直接交渉する方法と、②交渉自体は当事会社やアドバイザーが行うが特別委員会は随時指示や要請を行う方法とが挙げられています。
従前の実務では、特別委員会の交渉に対する姿勢についての整理が曖昧であったこともあり、上記①②が初期段階で決定されないままプロジェクトが進行されることもありました。交渉主体が明確化されるのが遅れると、交渉期間が短縮されたり、相手方の提示条件が徐々に既成事実化していくことなどにより、交渉の可能性や機会が限られてしまうことが懸念されます。
今後は、特別委員会としては適切な交渉過程が機能するよう、当事会社と委員会の交渉に関する適性と、起用する第三者算定機関の業務範囲(対応可能範囲)を初期段階で把握し、委員会としての①②に対する推奨や決定を委員会の組成段階で行うべきであると考えられます。
3. 3 株式価値算定とフェアネスオピニオンの意義・機能
従前の実務においても第三者評価機関による株式価値算定を取得する実務は定着しており、筆者の知る限り、特にMBOではすべての事例において同様の実務が採用されていました。一方、フェアネスオピニオンについてはその性質についての理解度が本邦において必ずしも高くなかったと考えられ、取得するか否かは企業の判断によりさまざまであったといえます。
本指針においては、株式価値算定とフェアネスオピニオンの意義と果たすべき機能の整理がなされました。特に、フェアネスオピニオンの意義について本邦における公表物で明確に整理されたのは、2007年に日本公認会計士協会がとりまとめた「企業価値評価ガイドライン」以来となります。フェアネスオピニオンを発行する主体に関する要件が規範化されていないことの問題意識についても触れつつ、その要件について本邦において初めて整理がなされたのも特徴的です。
ⅰ) 株式価値算定の意義・機能
また、株式価値算定の内容が対象会社の一般株主に対して開示されることにより、一般株主が取引条件の妥当性を判断する際の重要な判断材料となるという機能も有する(視点2)。
ⅱ) フェアネスオピニオンの意義・機能
また、欧米等では、構造的な利益相反の問題が存在するM&A等において取引条件の妥当性等に関する重要な参考情報としてフェアネス・オピニオンを取得することは一般的なプラクティスであると指摘されており、国際的に活動する投資家も含めた一般株主に対する説明責任を果たすという観点からも、その有用性が指摘されている(視点2)。
フェアネス・オピニオンとは、一般に、専門性を有する独立した第三者評価機関が、M&A等の当事会社に対し、合意された取引条件の当事会社やその一般株主にとっての公正性について、財務的見地から意見を表明するものをいう。
ⅲ) フェアネスオピニオンの発行主体
そのため、対象会社の取締役会や特別委員会は、第三者評価機関を選定するに当たっては、これらの要素も考慮して検討することが望ましい。
本指針で整理された株式価値算定とフェアネスオピニオンの意義・機能、フェアネスオピニオンの発行主体としての適格性は、今後の実務においてフェアネスオピニオンの取得が検討されるにあたり、当事会社の取締役会や特別委員会の理解を助けるものになると想定されます。
3. 4 第三者評価機関の独立性
第三者評価機関に独立性が求められることはもちろんのことですが、独立性に関する具体的な基準があるわけではないため、従前の実務ではやや曖昧に運用されていたきらいがあります。
本指針では、独立性の懸念が生じる状況として、第三者評価機関がM&Aの成否に関して利害関係を有している場合が挙げられています。
もっとも、例えば、当該第三者評価機関が買収者に対して自ら買収資金の融資その他の資金提供も行う場合のように、当該第三者評価機関が当該M&Aの成否に関して深刻な利害関係を有している場合には、その独立性に対する懸念が相当程度大きくなることから、基本的には上記の機能を果たす上で望ましくないと考えられるが、合理的な必要性からやむを得ずこのような事態に至る場合には、当該M&Aにおいて当該第三者評価機関が得る経済的利益の内容を開示する等、少なくともその独立性や利害関係の内容について十分な説明責任が果たされるべきである。
ここで記載される第三者評価機関が得る経済的利益の開示については以下のように記載されています。
注記では、「当該第三者評価機関自身が深刻な利害関係を有している場合だけでなく、そのグループ会社が深刻な利害関係を有している場合においても、両社の実態上の関係次第では実質的に同様の第三者評価機関の独立性に対する懸念が生じ得るとの指摘がある。」旨の記載もなされています。
3. 5 株式価値算定に関する開示
株式価値算定がその機能を発揮するためには、その内容が十分に開示されることが重要となります。従前においても、同様の観点から証券取引所の規程や金融商品取引法および関連諸法令が度々改正され、その都度開示の範囲が広がってきた経緯があります
本指針においては、算定に用いた資料の適切性等や検討過程に関しても、さらなる詳細な開示が求められました。
(例えば、①DCF法を用いて株式価値算定を実施した場合における(i)算定の前提とした対象会社のフリー・キャッシュフロー予測、およびこれが当該M&Aの実施を前提とするものか否か、(ii)算定の前提とした財務予測の作成経緯(特別委員会による事業計画の合理性の確認や第三者評価機関によるレビューを経ているか否か、当該M&A以前に公表されていた財務予測と大きく異なる財務予測を用いる場合にはその理由等)、(iii)割引率の種類(株主資本コストか加重平均資本コストか等)や計算根拠、(iv)フリー・キャッシュフローの予測期間の考え方や予測期間以降に想定する成長率等の継続価値の考え方等、②類似会社比較法を用いて株式価値算定を実施した場合における類似会社の選定理由に関する情報)
従前から、証券取引所の適時開示規制により、財務予測の内容や用いた割引率と成長率、類似会社の開示は求められていました。しかしながら本指針においては、財務予測の作成経緯や予測期間設定の考え方、類似会社の選定理由の開示まで求められています。
前提とした資料が不適切であれば、適切な株式価値算定結果は得られません。本指針の意義は、用いた表面的な数値だけでなく、どのような検討過程でその数値が用いられたのかまでの開示が求められた点にあるといえます。
4. おわりに
本稿では、本指針が株式価値算定実務に与える影響に焦点を当てて解説を行ってきました。株式価値算定はM&Aの取引条件に関する取締役会および特別委員会の意思決定に最も影響を与える重要な手続の一つです。本指針の公表によって従前に比べてより適切で透明性の高い算定実務で形成されていくものと期待されます。
また、冒頭で触れたとおり、M&Aが実行後に株主と当事会社の裁判に発展した場合、一般に公正と認められる手続が行われていたか否かが最大の焦点となります。この観点からも、本指針が実務に与える影響は大きいと考えられます。
以上
References
| 1. | ↑ | 東京証券取引所 企業行動規範に関する規則第12条の2 |
| 2. | ↑ | 特別委員会が独自にアドバイザーを起用した事例としては、2011年2月3日公表カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社のMBOと、2019年2月12日公表KDDI株式会社によるカブドットコム証券株式会社に対する公開買付けがあります。 |
M&A・組織再編のレポートを見る
-
はじめに 2025年7月22日、東京証券取引所(以下「東証」という。)による「MBOや支配株主による完全子会社化に関する上場制度の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正」(以下「本改正」...
-
上場企業によるM&A投資基準策定の動き~コーポレートガバナンスコード改訂との関連~(2025年9月号)
はじめに 上場企業によるM&A投資資金枠にかかるIR開示事例が増加傾向にあります。当社グループの顧客企業からは、M&A強化の次の課題として、投資判断基準を定義したいとの声が多く聞かれるように...
-
海外会社の企業価値評価:DCF法における重要ポイント(2025年8月号)
はじめに 企業価値評価の目的は多岐にわたり、M&Aにおける事業や株式の取得・譲渡、グループ内再編、さらには財務報告でのれんの減損テストや株式持分の公正価値評価など、多くのご依頼をいただいてお...
-
公正なM&A指針公表後5年間における特別委員会/フェアネス・オピニオン実務の変化(2024年07月31日号)
Topic. ► 公正なM&A指針公表後5年間における特別委員会/フェア...
-
「資本コスト経営」の視点で読み解く継続価値(2024年5月31日号)
Topic. ► 「資本コスト経営」の視点で読み解く継続価値 ...
-
株式交付制度公表事例による株価算定手法分析等の追跡調査(2023年08月31日号)
Topic. ► 株式交付制度公表事例による株価算定手法分析等の追跡調査 ...
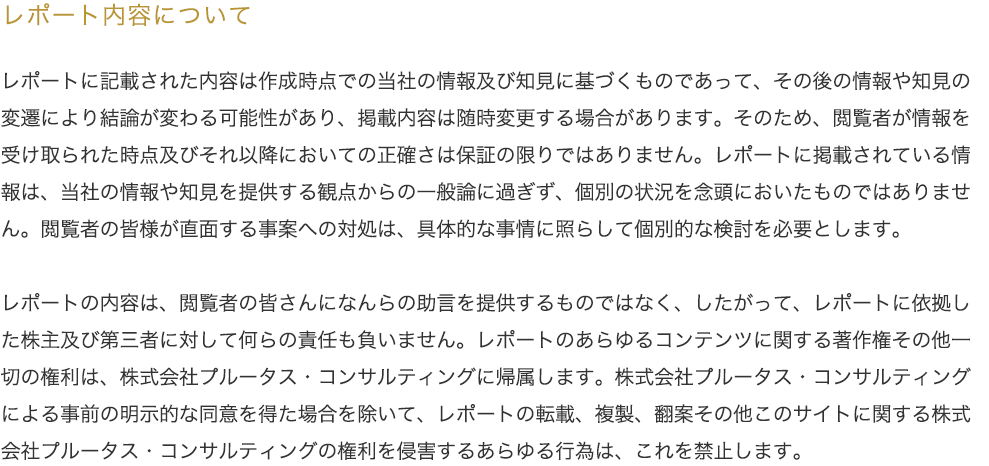
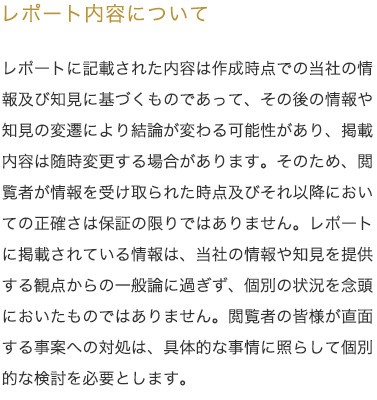
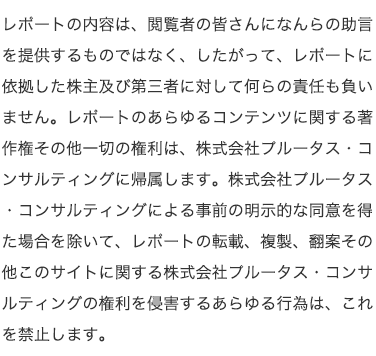
M&A・組織再編の事例を見る
-

株式会社ヘッドウォータースとBBDイニシアティブ株式会社の経営統合における助言の提供及び合併比率の算定
株式会社ヘッドウォータース(東証グロース 4011)とBBDイニシアティブ株式会社(東証グロース 5259)の経営統合に際し、吸収合併存続会社となる株式会社ヘッドウォータースのファイナンシャル・アドバ
続きを読む
-

イオン株式会社による株式会社サンデーの完全子会社化における株式価値の算定
イオン株式会社(東証プライム 8267)による株式会社サンデー(東証スタンダード 7450)の完全子会社化を目的とした株式公開買付けに際し、株式会社サンデーが公正性担保及び利益相反回避のために設置した
続きを読む
-

ラクスル株式会社のMBOにおける株式価値の算定
ラクスル株式会社(東証プライム 4384)のマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われる普通株式の公開買付けに際し、ラクスル株式会社が設置した特別委員会の第三者算定機関として株式価値算定書を
続きを読む
M&A・組織再編のソリューションを見る
-
株価算定
株価算定 エクイティファイナンス、M&A、TOB、自社株買いなど、株式や事業の譲渡、移転を伴う取引価格の決定、裁判における価格の立証、会計処理を前提とした評価額の算定など様々な目的に応じ、第
-
合併・株式交換・株式移転
合併・株式交換・株式移転 合併・株式交換・株式移転に際して株式価値を算定する場合、それぞれの企業の価値を別個に算定するときよりも、考慮すべき要素は多岐にわたります。これは、複数の企業を整合的な手法に
-
TOB
公開買付け(TOB、take-over bid) 一定数以上の上場株券等を買付ける目的で公開買付けを実施する場合には、公開買付届出書により通常の取引よりも厳格な情報開示が求められ、その範囲は公開買付
-
MBO
非公開化・MBO(Management Buyout) 抜本的な経営改革の手段として、MBOを含む非公開化が選択される場合、買手と少数株主の間に構造的な利益相反が存在することから、公正性の担保が重要
-
スクイーズアウト
スクイーズアウト 少数株主からの強制取得、いわゆるスクイーズアウトがなされる局面としては、非公開化・MBOの一環として行われる場合の他、取引先の非上場会社を完全子会社化する場合、分散した株式を創業家
-
債権譲渡
債権譲渡 グループ会社間取引やM&A取引において、金融債権が独立して譲渡される場合があります。 プルータス・コンサルティングの強み プルータスは、これまで培った豊富な評価経験及び金融債権

