レポート/メールマガジン
REPORTS
プロがまとめた調査・考察レポートを無料公開中
レポート/メールマガジン
No.
89
企業価値評価の前提となる事業計画の有用性とは
1. はじめに
株式価値評価の手法には、事業計画を前提に将来のフリー・キャッシュフローの割引現在価値をもって事業価値とするDCF(Discounted Cash Flow)法があり、事業計画の前提次第で評価結果は大きく変化する。そのため、評価人は、株式価値評価の過程で事業計画の有用性に関する分析を重視しなければならない。
一方で、「依頼者から提供された情報に関して、真実性・正確性・網羅性について検証せず、真実・正確・網羅的であることを前提にしている」旨の記載さえあれば、事業計画に問題があっても評価人の責任は免れると誤解し、事業計画の有用性に関する分析を軽視した株式価値評価が粉飾決算に利用された事件が発生した。日本公認会計士協会は、このような誤解を払拭するため、平成25年7月3日付で、経営研究調査会研究報告第32 号「企業価値評価ガイドライン」を改正した。
本稿では、「企業価値評価ガイドライン」改正の経緯を紹介した上で、事業計画の有用性に関する分析について解説する。
2. 「企業価値評価ガイドライン」の改正
日本公認会計士協会は、平成25年7月3日付で、経営研究調査会研究報告第32 号「企業価値評価ガイドライン」を改正し、主な改正内容として以下の説明がなされている。
・ 企業価値評価における算定業務の性格を明確に記載(算定結果を、批判的に検討する検討人が存在することを、強く意識して、業務を行う必要がある旨も記載)
・ 注意喚起の充実 |
本改正は、公認会計士の株式価値評価が上場会社の粉飾事件に利用されたことを踏まえて行われた。当該粉飾事件での株式価値評価は、事業ほとんど行っていない会社について、急成長する事業計画を前提に株式価値を数百億円とする算定をしたものである。
このような非現実的な事業計画を鵜呑みにした株式価値評価につき、「依頼者から提供された情報に関して、真実性・正確性・網羅性について検証せず、真実・正確・網羅的であることを前提にしている」旨の記載(以下、「Disclaimer」という。)さえあれば、事業計画に問題があっても評価人の責任は免れるのではないかと指摘する声が見受けられたことから「企業価値評価ガイドライン」が改正された。
改正前の「企業価値評価ガイドライン」においても、「入手した資料に関するこれらの検証に代えて、評価に際して採用できるかといった有用性の観点からの検討分析が必要である。」としており、入手した資料を鵜呑みにして良いわけではなく、Disclaimerの記載があっても責任を負う旨の整理をしていたが、より明確にすることを目的に改正されたものである。
3. Disclaimerの意義と有用性の観点からの検討分析の意義
株式価値評価は、依頼者から提供された情報を前提にして行われる。これらの情報には、過去の財務諸表(決算書)や事業計画等が含まれる。過去の財務諸表が監査済みで、監査人によって適正意見が表明されているならば信頼性が確保されていると考えることができる。しかし、監査を受けていなければ、不適切な会計処理が存在する可能性がある。株式売買等の取引を目的とした株式価値評価のために監査と同じ手続を必要とするならば、取引コストに見合わない莫大なコストが必要となる。さらに多大な工数をかけると取引の意思決定のために想定されるスケジュール内に株式価値評価が完了せず、実務上の要請に応えることができない。また、事業計画は、将来予測数値であり、予測された結果と実際の結果が相違することは当然のことであり、評価人はその達成可能性に関して責任を負えるものではない。
このように価値評価に際しては、実務上、提供された情報が真実・正確・網羅的であるとの前提に基づいて業務を遂行するのであり、評価人は、提供される情報の真実性・正確性・網羅性について原則として検証する義務を負うものではない。したがって、情報に関するこれらの欠如に起因して生じる問題から評価人が免責される配慮が必要であり、ここにDisclaimerの必要性が生じるのである。
一方で、株式価値評価を依頼する側は、単なる機械的な算定を期待するのではなく、専門家としての分析を踏まえた株式価値評価を期待するものと考えられる。そのため、「数値予想の前提条件の合理性、予測過程の合理性、作成数値の社内承認や外部公表、さらには、過去の実績値や信頼できる外部情報等との整合性に関して、検討・分析することが必要とされる。提供された非常識・非現実的な将来情報を無批判に受け入れ、機械的にそれを評価に使用するのではなく、批判性を発揮して、基礎資料としての有用性及び利用可能性の判断を行うことが重要である。1)「企業価値評価ガイドライン」Ⅰ 総 論 4.本ガイドラインを利用する際の留意点と価値評価の限界 (2) 提供される情報の検証より。」
したがって、提供された情報の有用性に関する分析が重要であり、専門家であれば発見できる不合理な前提を見逃すと評価人の責任が問われるのであり、評価人はこの点に留意する必要がある。
4. 事業計画の有用性に関する分析
事業計画の有用性に関する分析は、以下のようになされるものと考えられる。
(1) 過去の財務諸表の比較分析
ベンチャー企業等の設立間もない企業を除く評価対象会社は、事業実績があるため、過去の取り組みを起点にして将来の見通しを考え事業計画が策定されることになる。
したがって、事業計画の有用性に関する分析は、過去の業績を分析することから始まる。過去の業績分析は、財務諸表の比較分析が基本となり、主要な増減について原因を質問し回答を受けることにより、過去のフリー・キャッシュフロー実績の増減要因を理解することで、フリー・キャッシュフロー実績の流れを把握する。
(2) 過去の業績推移と事業計画の推移との比較
過去のフリー・キャッシュフローの実績推移を把握したら、過去のフリー・キャッシュフローと事業計画のフリー・キャッシュフローとを比較し、事業計画のフリー・キャッシュフロー増減に関する理由を確認することで、事業計画の前提の合理性を分析することができる。この過程で前提の根拠があいまいであれば、事業計画の修正も必要になる場合もある。
(3) 事業計画の策定期間
DCF法による株式価値評価は、一定期間経過後の会社の存続期間の価値を継続価値として単純な公式で算定される。これは、一定期間経過後業績が安定していることを前提にしており、少なくとも業績が安定するまでの期間を予測期間とし、フリー・キャッシュフローを見積もる必要がある。
一方で、事業計画は一般的に、中長期の事業戦略を検討することが目的であり、計画期間は、3年間から5年間とすることが多い。この期間は、必ずしも業績が安定するまでの期間とは限らない。
したがって、想定される投資の効果が安定するまでの期間となっているかを確認すべきであり、事業計画の策定期間を延長することが必要な場合は、そのような対応を依頼する。
5. ベンチャー企業の事業計画の有用性に関する分析はどうするか
ベンチャー・キャピタルは、新しい市場を作り出す新技術等への期待から設立間もないベンチャー企業に投資することも多い。また、この際の価格根拠を上場審査の観点から求められることが多い。
しかしながら、ベンチャー企業等の設立間もない企業は、過去業績の実績がないことから、事業計画の有用性を分析することは困難である。
一方で、このようなベンチャー企業の株式価値評価は、No.67「ベンチャー企業の株式価値評価に関する論点整理」(October 30,2015)で解説したとおり、上場企業のM&Aで株主価値をDCF法で算定する場合の割引率の水準と異なり、ベンチャー企業にDCF法を適用する際の割引率は、高いリスクを考慮する必要があり、それはベンチャー・キャピタル等の投資家による期待利回りを採用すること対応することが考えられる。それが、ベンチャー・キャピタルの期待利回り(Internal Rate of Return、IRR)である。このIRRは、設立して1年以内のベンチャー企業であれば、60%、70%といった高い水準が想定されるのであり、失敗するリスクが織り込まれている。
それ故、このIRRに対応する将来のフリー・キャッシュフローの前提は、実現しない可能性もあり得ることを想定したものでなければならず、成功した場合の最大限のフリー・キャッシュフローを想定すべきである。したがって、ベンチャー企業の事業計画については、成功した場合、新たに生み出される市場規模の想定やシェアから策定されるものであり、この観点から事業計画の根拠を確認するのであり、実現可能性の観点から検討するものではないものと考えられる。
以上
References
| 1. | ↑ | 「企業価値評価ガイドライン」Ⅰ 総 論 4.本ガイドラインを利用する際の留意点と価値評価の限界 (2) 提供される情報の検証より。 |
M&A・組織再編のレポートを見る
-
はじめに 2025年7月22日、東京証券取引所(以下「東証」という。)による「MBOや支配株主による完全子会社化に関する上場制度の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正」(以下「本改正」...
-
上場企業によるM&A投資基準策定の動き~コーポレートガバナンスコード改訂との関連~(2025年9月号)
はじめに 上場企業によるM&A投資資金枠にかかるIR開示事例が増加傾向にあります。当社グループの顧客企業からは、M&A強化の次の課題として、投資判断基準を定義したいとの声が多く聞かれるように...
-
海外会社の企業価値評価:DCF法における重要ポイント(2025年8月号)
はじめに 企業価値評価の目的は多岐にわたり、M&Aにおける事業や株式の取得・譲渡、グループ内再編、さらには財務報告でのれんの減損テストや株式持分の公正価値評価など、多くのご依頼をいただいてお...
-
公正なM&A指針公表後5年間における特別委員会/フェアネス・オピニオン実務の変化(2024年07月31日号)
Topic. ► 公正なM&A指針公表後5年間における特別委員会/フェア...
-
「資本コスト経営」の視点で読み解く継続価値(2024年5月31日号)
Topic. ► 「資本コスト経営」の視点で読み解く継続価値 ...
-
株式交付制度公表事例による株価算定手法分析等の追跡調査(2023年08月31日号)
Topic. ► 株式交付制度公表事例による株価算定手法分析等の追跡調査 ...
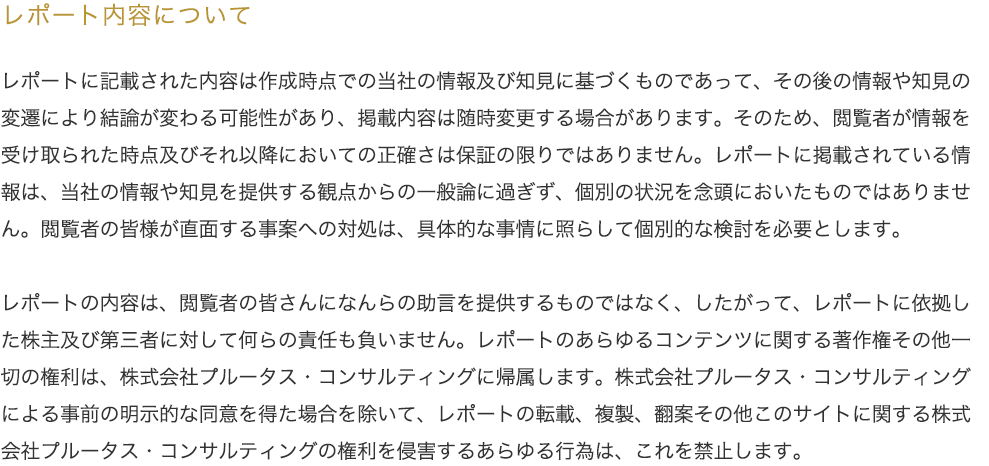
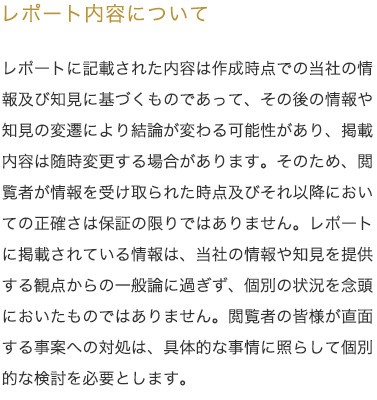
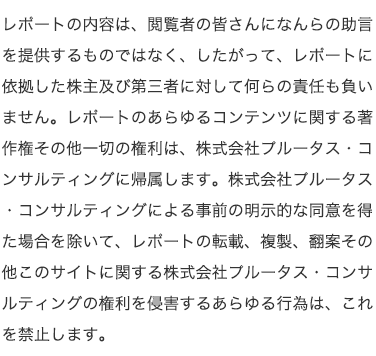
M&A・組織再編の事例を見る
-

株式会社ヘッドウォータースとBBDイニシアティブ株式会社の経営統合における助言の提供及び合併比率の算定
株式会社ヘッドウォータース(東証グロース 4011)とBBDイニシアティブ株式会社(東証グロース 5259)の経営統合に際し、吸収合併存続会社となる株式会社ヘッドウォータースのファイナンシャル・アドバ
続きを読む
-

イオン株式会社による株式会社サンデーの完全子会社化における株式価値の算定
イオン株式会社(東証プライム 8267)による株式会社サンデー(東証スタンダード 7450)の完全子会社化を目的とした株式公開買付けに際し、株式会社サンデーが公正性担保及び利益相反回避のために設置した
続きを読む
-

ラクスル株式会社のMBOにおける株式価値の算定
ラクスル株式会社(東証プライム 4384)のマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われる普通株式の公開買付けに際し、ラクスル株式会社が設置した特別委員会の第三者算定機関として株式価値算定書を
続きを読む
M&A・組織再編のソリューションを見る
-
株価算定
株価算定 エクイティファイナンス、M&A、TOB、自社株買いなど、株式や事業の譲渡、移転を伴う取引価格の決定、裁判における価格の立証、会計処理を前提とした評価額の算定など様々な目的に応じ、第
-
合併・株式交換・株式移転
合併・株式交換・株式移転 合併・株式交換・株式移転に際して株式価値を算定する場合、それぞれの企業の価値を別個に算定するときよりも、考慮すべき要素は多岐にわたります。これは、複数の企業を整合的な手法に
-
TOB
公開買付け(TOB、take-over bid) 一定数以上の上場株券等を買付ける目的で公開買付けを実施する場合には、公開買付届出書により通常の取引よりも厳格な情報開示が求められ、その範囲は公開買付
-
MBO
非公開化・MBO(Management Buyout) 抜本的な経営改革の手段として、MBOを含む非公開化が選択される場合、買手と少数株主の間に構造的な利益相反が存在することから、公正性の担保が重要
-
スクイーズアウト
スクイーズアウト 少数株主からの強制取得、いわゆるスクイーズアウトがなされる局面としては、非公開化・MBOの一環として行われる場合の他、取引先の非上場会社を完全子会社化する場合、分散した株式を創業家
-
債権譲渡
債権譲渡 グループ会社間取引やM&A取引において、金融債権が独立して譲渡される場合があります。 プルータス・コンサルティングの強み プルータスは、これまで培った豊富な評価経験及び金融債権

