レポート/メールマガジン
REPORTS
プロがまとめた調査・考察レポートを無料公開中
レポート/メールマガジン
No.
151
提案型サービスとしての資本コスト算定(2023年11月30日号)

Topic. ► 提案型サービスとしての資本コスト算定
本稿の目的
割引率の算定は、インカム・アプローチによる企業価値評価における重要な工程の一つですが、近年は割引率の算定を単独で受託する事例が増えました。その多くは、会計処理の一環として行われる海外投資の評価を目的とするものです。
会計処理に関連して、企業価値評価の手法を援用しつつ割引率が算定される場面の一例としては、いわゆる減損会計における使用価値を算定するための割引率が挙げられ、我が国の会計基準においても加重平均資本コストを用いることが適当とされています。
しかしながら、減損会計における割引率の算定にあたっては、資産または資産グループ固有のリスクの反映という観点が重視され、取引目的の評価における割引率の算定と似て非なる面が出てくる場合も散見されます。しかも、海外投資の評価に用いる割引率を算定するにあたっては、各国市場のデータにそのまま依存できない場合が大半で、信頼性の高い市場のデータに依拠しつつ、それらの市場と各国市場の違いを適宜調整するのが基本となります。そのために必要な調整の手法については様々なものが存在することから、専門性を有する第三者機関へ委託することの実益が大きい領域といえます。
このような特殊性に加え、我が国の企業活動における海外投資の拡大と会計監査の厳格化によって、会計目的の評価における割引率の算定に関する意識が高まり、それが案件数の増加をもたらす一因となっているようです。
海外投資の評価において最も特徴的な点は資本コスト、特に株主資本コストの算定に表れます。海外投資の評価においても、資本資産価格モデルに依拠する点は同様で、式の形自体は大きく異なりません。しかしながら、単純な一次式により算定されているようであっても、変数の選択肢の幅は国内投資の評価に比べて格段に広がります。しかも、割引率の算定が会計処理の一環として行われる場合には、先述の通り企業固有の事情を反映させるための配慮を求められる場合があります。
そのため、企業価値評価上も会計上も妥当な結論を導く上では、定型化されたモデルに基礎数値を当てはめる受動的な形ではなく、依頼主の目的に適ったものを提案する、より能動的な形での関与が第三者評価機関には必要と感じています。端的にいえば、請負型から提案型への転換が迫られているということです。
本稿では、取引目的の評価と対比しつつ、会計目的の評価の特殊性を明らかにするとともに、第三者評価機関による提案の果たす役割を、事例を交えて紹介したいと思います。
会計目的と取引目的の評価の異同
会計目的と取引目的の評価において本質的に異なる点は、最終的な結果に経営者の見積もり、判断が織り込まれるかどうかにあると筆者は考えます。
取引目的の評価は、価格の公正性を担保するために行われる関係上、依頼主の主観を排した客観的、中立的な立場から実施することに重きが置かれます。第三者評価機関は、依頼主から提供を受けた事業計画、財務諸表その他の資料に依拠するものの、市場のデータに基づいて集計される割引率の算定は専ら第三者評価機関の責任において行われ、経営者の見積もり、判断が介入する余地はありません。
これに対して、会計上の数値は経営者による見積もり、判断を反映したものとなります。このような性格上、その前提となる割引率を求めるにあたっても、経営者の見積もり、判断を合理的な限度において反映させることは差し支えなく、むしろ必要と考えられます。
もう一つの違いは、企業固有の事情の反映という観点が重視されることです。企業価値評価上、このような事情はいわゆる固有リスクに相当し、市場リスクと対比されます。企業価値の変動要因が一部の企業にだけ影響し、その他の企業に影響しない場合、その変動要因を固有リスクといいます。
これに対して市場リスクとは、企業価値の変動に遍く影響を及ぼす市場の一般的な要因です。特に会計目的の評価において重視される固有リスクとしては、評価対象企業の時価総額に応じた規模リスク、国・地域に応じたカントリーリスクが挙げられます。具体的には、小規模企業には規模リスク、新興国の企業にはカントリーリスクが存在するため、資本コストもそれに応じて引き上げられるべきというのが典型的な主張です。
しかしながら、理論上資本コストに影響を及ぼすのは分散不能な組織的リスクに限られ、完全資本市場においては市場リスクのみが組織的リスクとなります。これに対して固有リスクは、市場における価格調整を通じて分散される非組織的リスクと位置付けられ、資本コストには影響を及ぼさないとされています。実際の市場における価格調整機能には限界があることから、固有リスクの一部が分散しきれず、組織的リスクとして残るということは理論上も想定されるものの、あくまで一部がそうなり得るに過ぎません。いずれにしても、固有リスクが存在するというだけでは資本コストを引き上げる直接の根拠にならず、分散不能であって初めて加算が正当化されるということです。
それにもかかわらず、企業固有の事情の反映という名目で様々な項目が機械的に加算された場合、算定された割引率には本来分散されて解消するはずのリスクが反映されるばかりか、実質的に同じ要因に基づく加算が二重に適用されることにもなりかねず、理論的には大いに問題がある手法と位置付けられます。したがって、客観性、中立性がとりわけ強く要請される取引目的の評価においては、企業固有の事情を反映させる余地を極力狭く解すべきと筆者は考えます。
第三者評価機関の役割
先述した特殊性に起因して、会計目的の評価においては、取引目的の評価と同様に一切の主観を排した客観的、中立的な立場から割引率を求めるよりも、評価の前提となった会計事象に関する依頼主の判断を適切に反映するための手法を提案する形の方が依頼主の目的に適う場合があります。会計処理の一環として割引率が算定される以上、会計事象に関する依頼主の判断が適切に反映され、監査上も是認される前提が置かれなければならず、第三者評価機関の独善では解決しないということです。
例えば、会計上企業固有の事情の反映という観点が重視され、依頼主も同様の観点で会計処理を検討しているにもかかわらず、理論的な欠陥を有することを理由に、第三者評価機関として資本コストに対する一切の加算を否定した場合、算定された割引率は依頼主にとって意味のないものとなりかねません。したがって、このような場合には、依頼主が反映すべきと考える固有の事情について理解し、過度に客観性を犠牲にしない限度において反映させるための方法を提案することが依頼主の目的に適うといえます。
ただし、実務慣行として存在する限り、あらゆる手法を任意に選択できるわけではありません。会計目的の評価においても客観性、中立性が度外視されてはならないところ、割引率の算定に用いられる手法はそれぞれ一定の前提条件を有しており、同時に成立しない条件に基づく手法が併用された場合は、不合理な評価となってしまうからです。したがって、提案にあたっては、自身が原則的には採用しないものも含めて、様々な割引率の算定技法を前提条件とともに理解し、依頼主の目的に合致したものを提案する必要があり、第三者評価機関の力量により差がつきやすい分野といえます。
事例
割引率の算定に関する提案といっても、具体的には想起できないかもしれません。そこで、筆者が担当した事例を一般化しつつご紹介したいと思います。
信用スプレッドの急上昇への対応
資本資産価格モデルで株主資本コストを求め、負債資本コストと加重平均するという方法は、海外投資の評価においても異なりません。このことから、一度モデルを作成すれば、そのモデルを継続的に利用して、基礎数値だけ更新すればよいと思われるかもしれません。しかし、海外投資の評価に用いる割引率の水準は、突発的な要因によって大きく変動しがちです。直近では、昨年初頭に東欧で表面化した政情不安が挙げられます。
依頼主様は、従来から外部機関に委託することなく、海外投資の評価に用いる割引率を独自に計算していらっしゃいました。株主資本コストを求めるにあたっては、資本資産価格モデルで計算した値に対して、社内所定の基準により算定される割合を加算する方法が採用されており、その割合は主として各国の格付に応じた信用スプレッドに依存するものでした。しかしながら、昨年の2月以降、一部の国の格付が大きく引き下げられるとともに、同じ格付に対応する信用スプレッドが急上昇したことにより、従来の基準をそのまま踏襲すると、計算される割引率が数十%にも達することが判明しました。しかしながら、先方としては、評価対象企業の実態が大きく変わらないにもかかわらず、外部環境の変化によって資本コストが急上昇することに違和感があるとして、対応策に関するご相談をお寄せいただいたものです。
海外投資の評価にあたって、各国の市場環境の違いを反映した加算をする実務の中でも、国別の信用スプレッドを利用する手法は、客観性の高さにおいて他の手法を上回るため、広く採用されてきたという実態があります。信用スプレッドは、短期的な市場の混乱によって大きく変動しやすい傾向があり、最近では新型コロナウイルス感染症の世界的な流行拡大局面においても急上昇が起こりました。このような問題点を回避するためには、一時点の信用スプレッドに依存することなく、一定期間の平均的な格付を基準としてスプレッドを定量化したり、株価指数のボラティリティの相対比を利用したモデルを併用したりといった対応が有効と考えられます。しかしながら、依頼主様としては、従来採用してきた方法からの継続性にも鑑み、一定期間のデータを利用することにより短期的な変動を平準化する方法については消極的な立場とのことでした。そこで、一時点の格付に基づく信用スプレッドを用いる手法自体は踏襲しつつも、従来採用されてきた社内所定の基準に代え、より客観性が高いと思われる外部の情報源からデータを取得することを提案し、ご採用いただくに至りました。
減損処理の検討に用いる割引率の算定
依頼主様は、新興国で展開する事業の採算性の悪化に伴い、投資勘定の減損処理を検討する必要性に迫られていました。その結論は、減損処理自体は回避しがたいものの、損失として処理される金額を合理的な範囲に収めたいというものでした。ただし、株主資本コストを構成する無リスク利子率及びリスク感応度と負債資本コストについては、基準日またはそれ以前における市場のデータに依存し、見積もりの幅がほとんど生じないため、実質的には株主資本コストの前提となる株式リスクプレミアムの水準と、株主資本コストに対する加算をどのように取り扱うかが問題でした。
海外、特に新興国における投資は、国内投資にはない様々なリスクに晒されるものと認識されており、これを理由に資本コストに対して様々な加算が適用されがちです。しかしながら、理論上、資本コストに影響するのは分散不能な組織的リスクに限られ、資本コストへの加算を検討するにあたっても、分散不能かどうかという観点から検討されるべきところ、実務家の間でそのような理解が浸透しているとはいいがたいのが現状です。そこで、実務上考慮されることの多い規模リスク及びカントリーリスクの論拠について解説するとともに、それぞれに応じた加算を適用しないことに妥当性が認められるための条件についてとりまとめ、会計監査人との間でご協議いただいたところ、いずれの加算も適用せずに割引率を求めることとなりました。
結語
会計処理に関連して割引率を算定する目的は、取引目的の評価以上に様々です。それらの目的に合致した妥当な結論を導く上では、画一的な公式にデータを当てはめ計算するだけでは足りず、モデルの構築にあたって周到な配慮を要する場合が出てくることにつき、本稿を通じてご理解いただけたかと思います。想定外の難問に突き当たった場合は、第三者評価機関の積極的な活用をご検討いただければ幸いです。
執筆者紹介
明石 正道 < エグゼクティブ・リサーチャー 京都大学 経営管理大学院 研究員 >
一人旅を愛し、道中の顛末をblogに綴って十余年を重ねる。培われた文章表現を活かし「企業価値評価の実務Q&A」の執筆を初版から一貫して担当する。データ配信サービスValue Proの開発にも携わり、資本コストの算定に造詣が深い。
株式会社プルータス・コンサルティング 広報担当
〒100-6035 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング35階
TEL:03-3591-8123
※ 本メールは、プルータス・コンサルティング社員が名刺交換および面談させて頂いた皆様にお送りしております。配信停止のご希望は こちら から承ります。
情報発信 調査・研究のレポートを見る
-
「資本コストや株価を意識した経営の実現」に係る開示企業一覧表の見直しについて(2026年1月号)
はじめに 東京証券取引所(以下、「東証」という。)は、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」(以下、「資本コスト開示」という。)について2026年1月15日から資本コスト開示に...
-
はじめに 2025年7月22日、東京証券取引所(以下「東証」という。)による「MBOや支配株主による完全子会社化に関する上場制度の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正」(以下「本改正」...
-
東証MBO規則改正により想定される特別委員会/算定/フェアネス・オピニオン実務の変化
はじめに 2025年7月22日、東京証券取引所(以下「東証」という。)による「MBOや支配株主による完全子会社化に関する上場制度の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正」(以下、「本改正...
-
資本コスト経営のすすめ なぜあなたの会社はPBR<1倍なのか / 親子上場銘柄の非公開化の現在地と関連する動向(2025年5月号)
①資本コスト経営のすすめ なぜあなたの会社はPBR<1倍なのか 本書を執筆したきっかけ この度、弊社代表の野口が執筆した「資本コスト経営のすすめ なぜあなたの会社はPBR<1倍なのか」が刊...
-
-第3回- 我が国のPBRの俯瞰的な分析とPBRの影響要因の検討(2025年4月号)
第1回では、2017年末から2024年9月末までの時価総額と株主資本の推移を確認しつつ、PBRの等級別割合を市場別に確認した。すると、時価総額は2022年まで上下しつつも概ね同水準で推移した上...
-
2024年の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に係るフォローアップ内容の振り返り(2025年2月号)
はじめに 2023年3月31日に、東京証券取引所(以下「東証」という。)より「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」が公表されて以降、2024年12月末時点でプライム市場...
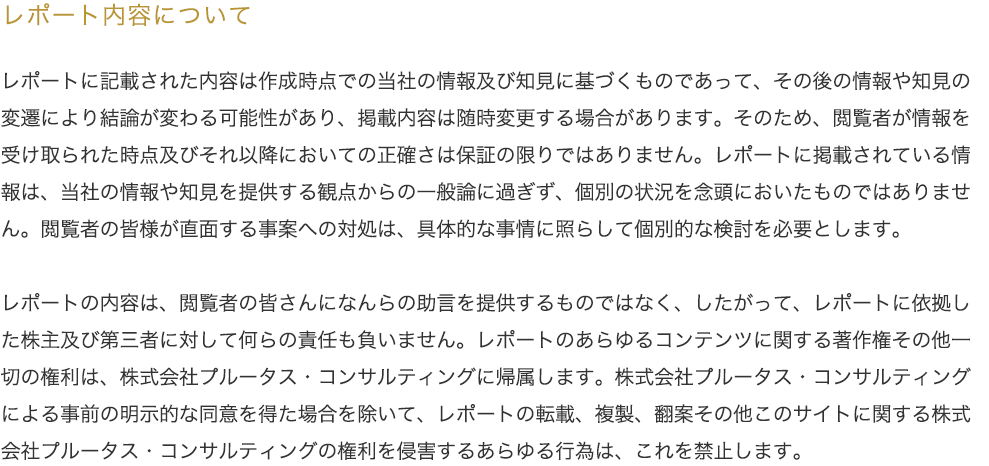
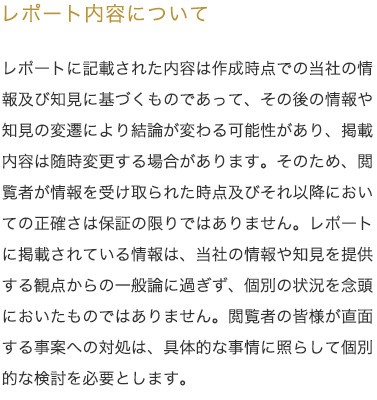
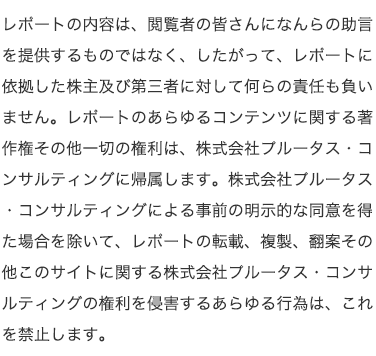
情報発信 調査・研究のソリューションを見る
-
Value Pro
企業価値(株式価値)の評価方式は、過去において、税務上の取扱いを準用するなどの方法が慣習的に採用されているケースがありましたが、現在では理論的に体系化されており、グローバル・スタンダードとして収益方式
-
Plutus+レポート
企業価値評価の第一線に立つ当社のコンサルタントが、時事の話題を独自の視点で分析したレポートです。平成22(2010)年以降に発表されたレポートを当サイトでご覧いただくことができます。皆様の実務にお役立
-
出版・寄稿
本邦屈指の豊富な事例の蓄積から得られた知見を、広く還元していくことも当社の使命の一つです。平成22(2010)年に初版が刊行された「企業価値評価の実務Q&A」は、分かりやすい解説が支持されて、
-
バリュエーション研究会
バリュエーション研究会 企業価値評価の実務においては、担当者の主観を排して画一的に処理するという思想が優先されるあまり、必ずしも理論的とはいえない取扱いが、一般的であるというだけの理由により無批判に
-
バリュエーションに関する社内指針の策定支援
バリエーションに関する社内指針の策定支援 従業員株主からの自社株買いなど、定型化された条件に基づいて反復継続的に行われる取引については、その都度第三者算定機関の評価を取得する必要性は乏しいといえます

